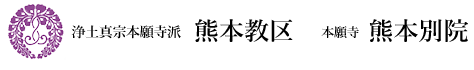法話集・寺院向け案内
読む法話「「また来るけんね」は母のよび声」 (八代市 種山組 大法寺 大松 龍昭)
2025/09/01 09:00
昨年の十月に九十七歳で往生した、私の母の話です。
九十を過ぎて次第に認知症が進んで以降、母は長姉の家に住まいを移し、そこで最後まで過ごしました。
亡くなる二か月ほど前のことです。発熱して母は近くの病院に入院しました。姉は母が寝たきりなることを心配し、熱が下がったら一旦退院させ、リハビリができる通所していた施設に移すつもりでした。しかし、私がその病院に初めて足を運んでその母の姿をみた時、「これはここを出ることはあるまい。きっとここが最後になるだろう」と私なりに気づきました。私はこれまで亡くなったご門徒さんの姿に何度も出あってきましたが、そのご門徒さんの姿とその時の母の姿が、完全に重なって見えたからです。なのでそれからは「次はない。これが最後なのだ」と自分に言い聞かせて見舞っていました。
ところが結果的に最後の見舞いとなったその日、看護師さんが「だいぶ食欲が落ちられました」と仰ったので、私は母に「ご飯は無理してでも食べなあかんよ」と声をかけ、母も理解したかのように二、三度頷きました。そしてその日、私は帰り際に母に「また来るけんね」と言ったのです。
確かに見舞いの帰りに「二度と来んけんね」と言って去る人はいないでしょう。「次に来るまで元気にしていてね」という思いで「また来るけんね」と言うのは、至って普通なことです。しかし、「次はない、これが最後だ」と自分に言い聞かせていた私は、この言葉がこの口から出たことに愕然としました。
この命は先送りなどできないものであること、明日とも今日とも知れない命をいま不思議にも生かされていること、したがってこの今を決して疎かにしてはならんのだということをこれまで何度も学んできたつもりだったのに、この口は「また来るけんね」と間違いなく言ったのです。
私は「やはりそうか」とつくづく思いました。どれほど大切なことですら、やすやすと忘れてしまう身の上の事実を忘れていたことを。だからこの命が尽きるまで、大切なことは繰り返し気づき直していかねばならないということを、また改めて母から学ばせてもらったのだと思ったことです。
そしてもう一つ思ったのは、「また来るけんね」は私が言うべき言葉ではなかったということです。親鸞聖人が「つつしんで浄土真宗を案ずるに、二種の回向あり。一つには往相、二つには還相なり」と明かされている通り、阿弥陀仏より施された(回向)お念仏の道とは、この私がお浄土へと行き生まれて仏と成る(往相)と同時に、仏と成るがゆえにこの娑婆世界に必ず還ってくる(還相)ということでありました。
どのようにしてこの私が仏縁に出あったかということについては、それぞれに背景がありましょう。ただ、自ら求めてというよりは、私が図らずして誰かに導かれて気がついたら出あっていた、ということが多いのではないでしょうか。例えば、あの人との別れという悲しみと痛みが縁となってこの教えに出あった、ということも少なくはないでしょう。
だとするならば、その私が称えるお念仏はそのまま仏と成った亡き方のお陰でこぼれたお念仏であり、その合わさった両手もまた仏と成った亡き方のお陰で合わさった両手ということになりましょう。そしてそこに気づかされてくると、この私の称えるお念仏の中に、この私の合わせた両手の中に、そのはたらきにいつだって出あえるのだということも明らかになってくるはずです。つまり仏と成った亡き方とは、私がお浄土に生まれねばあえないのではなく、いまここであえるということです。「還ってくる」とはそういうことを意味しているはずで、姿・形として見えてくるのではなく、はたらきとして感じ取り、聞き取っていくものだと私は思います。
そういう意味において、「また来るけんね」はそもそも私が言うべきものではなかったのです。「気づいている通り、私の死はもう間近だよ。でもね、心配はいらない。この命終えて速やかに仏と成って、貴方がお念仏を称えるその口元に、そして貴方が合わせるその両手の中に、必ず繰り返しまた還ってくるからね、そのことにどうか気づいておくれね」という、母のよび声でありました。そのように味わえた時に、母との別れがより一層尊いものに思えたことでありました。
九十を過ぎて次第に認知症が進んで以降、母は長姉の家に住まいを移し、そこで最後まで過ごしました。
亡くなる二か月ほど前のことです。発熱して母は近くの病院に入院しました。姉は母が寝たきりなることを心配し、熱が下がったら一旦退院させ、リハビリができる通所していた施設に移すつもりでした。しかし、私がその病院に初めて足を運んでその母の姿をみた時、「これはここを出ることはあるまい。きっとここが最後になるだろう」と私なりに気づきました。私はこれまで亡くなったご門徒さんの姿に何度も出あってきましたが、そのご門徒さんの姿とその時の母の姿が、完全に重なって見えたからです。なのでそれからは「次はない。これが最後なのだ」と自分に言い聞かせて見舞っていました。
ところが結果的に最後の見舞いとなったその日、看護師さんが「だいぶ食欲が落ちられました」と仰ったので、私は母に「ご飯は無理してでも食べなあかんよ」と声をかけ、母も理解したかのように二、三度頷きました。そしてその日、私は帰り際に母に「また来るけんね」と言ったのです。
確かに見舞いの帰りに「二度と来んけんね」と言って去る人はいないでしょう。「次に来るまで元気にしていてね」という思いで「また来るけんね」と言うのは、至って普通なことです。しかし、「次はない、これが最後だ」と自分に言い聞かせていた私は、この言葉がこの口から出たことに愕然としました。
この命は先送りなどできないものであること、明日とも今日とも知れない命をいま不思議にも生かされていること、したがってこの今を決して疎かにしてはならんのだということをこれまで何度も学んできたつもりだったのに、この口は「また来るけんね」と間違いなく言ったのです。
私は「やはりそうか」とつくづく思いました。どれほど大切なことですら、やすやすと忘れてしまう身の上の事実を忘れていたことを。だからこの命が尽きるまで、大切なことは繰り返し気づき直していかねばならないということを、また改めて母から学ばせてもらったのだと思ったことです。
そしてもう一つ思ったのは、「また来るけんね」は私が言うべき言葉ではなかったということです。親鸞聖人が「つつしんで浄土真宗を案ずるに、二種の回向あり。一つには往相、二つには還相なり」と明かされている通り、阿弥陀仏より施された(回向)お念仏の道とは、この私がお浄土へと行き生まれて仏と成る(往相)と同時に、仏と成るがゆえにこの娑婆世界に必ず還ってくる(還相)ということでありました。
どのようにしてこの私が仏縁に出あったかということについては、それぞれに背景がありましょう。ただ、自ら求めてというよりは、私が図らずして誰かに導かれて気がついたら出あっていた、ということが多いのではないでしょうか。例えば、あの人との別れという悲しみと痛みが縁となってこの教えに出あった、ということも少なくはないでしょう。
だとするならば、その私が称えるお念仏はそのまま仏と成った亡き方のお陰でこぼれたお念仏であり、その合わさった両手もまた仏と成った亡き方のお陰で合わさった両手ということになりましょう。そしてそこに気づかされてくると、この私の称えるお念仏の中に、この私の合わせた両手の中に、そのはたらきにいつだって出あえるのだということも明らかになってくるはずです。つまり仏と成った亡き方とは、私がお浄土に生まれねばあえないのではなく、いまここであえるということです。「還ってくる」とはそういうことを意味しているはずで、姿・形として見えてくるのではなく、はたらきとして感じ取り、聞き取っていくものだと私は思います。
そういう意味において、「また来るけんね」はそもそも私が言うべきものではなかったのです。「気づいている通り、私の死はもう間近だよ。でもね、心配はいらない。この命終えて速やかに仏と成って、貴方がお念仏を称えるその口元に、そして貴方が合わせるその両手の中に、必ず繰り返しまた還ってくるからね、そのことにどうか気づいておくれね」という、母のよび声でありました。そのように味わえた時に、母との別れがより一層尊いものに思えたことでありました。
[ カテゴリー: ]