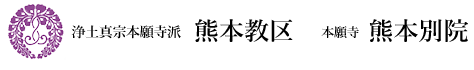法話集・寺院向け案内
新年のご挨拶 熊本教区教務所長・熊本別院輪番 大辻󠄀子 順紀
慈光迎春
お念仏とともに新年を迎えられましたこと、お慶び申しあげます。
さて、昨年は先の大戦終結から80年の節目の年でございました。終戦から80年以上経った今日、実際に戦争を体験されている世代が高齢化し、数少なくなられていることに加えて、これまでに経験したことのない異常気象が甚大な被害をもたらす自然災害に毎年のように直面するなどによって、戦争がもたらした計り知れないその悲しみは過去のこととして忘れ去られ、近い将来、平和実現のための取り組みが後回しになってしまうのではないかとの強い懸念を抱くことでございます。
80年前の7月1日そして終戦間近の8月10日、ここ熊本も大空襲を受け469人もの尊い命が犠牲になりました。終戦末期はこのように日本各地で空襲が激化し、全国で41万人もの民間人が犠牲になったと言われています。
そしてその終戦から80年の現代にあってもロシア連邦によるウクライナへ軍事侵攻やイスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突、イスラエル・イラン相互の軍事行動、そこへアメリカの軍事介入など、各地の紛争、内戦、争いは絶えることなく、罪のない多くの人々が命の危機に晒されています。
この日本においても「台湾有事」への備えと称して沖縄県の離島や鹿児島県の島に自衛隊基地が建設されており、さらには昨年の国会における首相の「存立危機事態発言」によって日中関係が冷え込み、決して「対岸の火事」ではありません。
言うまでもありませんが、戦争は人間によるもっとも愚かで醜い所業であり、いかなる理由があろうともそれは決して正当化されるものではなく、絶対に許されるべきことではありません。武力によって真の平和を実現することは、できないのです。しかし、私たちは長く続くことでそのことに慣れてしまい、関心が希薄になっていくことこそが、私たちにとって最も恐れなければならないことであり、無関心が私たちの最大の敵であり脅威であります。
釈尊は『法句経』に「己が身にひきくらべて、殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ。」と、どこまでも非暴力を貫く生き方をお説きくださいました。しかし我が教団は、先の大戦に積極的に加担したという過去の事実があります。そうした過去を謙虚に反省し、戦争がもたらす痛ましく悲惨な事実や数えきれないほどの悲しい死別の上に私たちが生かされているということ、犠牲になられた方々の無念さや思いを背負っていく責務があるということを次の世代へしっかりと伝えねばなりません。
そして親鸞聖人のお示しくださいました「世の中安穏なれ仏法ひろまれ」また「御同朋・御同行」とのお心にかなうよう、お念仏申させていただきながら、自他ともに心豊かに生きていくことのできる「非戦平和」の世界の実現に微力ながら努めさせていただくことでございます。
本年もお念仏を慶ばせていただきながら職員とともに精進してまいりますので、皆さまには引き続き、ご教導たまわりますようお願い申しあげ新年のご挨拶といたします。
合掌
読む法話「法を聞くということ」 (熊本市 託麻組 眞法寺 眞壁法城)
先日、私の住む校区で開催された「マイタイムライン研修」というものを受講しました。
マイタイムラインとは、災害の際の避難に向けての段取り表のことです。
前もって水害や台風などの災害に対して、
①いつ避難を始めるか
②何を持って避難するか
③どの道を通るのか
④どこに避難するか
などを決めて家族で情報を共有し、いざというときに備えておくことが大切だとのこと。
最近では「ハザードマップ(防災マップ)」とともに、自治体のホームページでその重要性が紹介され、小学校の社会の教科書などでも取り上げられているそうです。
色々とためになるお話を聞かせていただいたのですが、私にとって特に興味深かったのは、災害の際に、なぜ避難が手遅れになりがちなのかということについての説明でした。
そこには「正常性バイアス」と呼ばれるものが大いに関係しているということでした。
バイアスとは、偏見や先入観のことであり、人間の正常な判断を狂わせる原因となるものです。
「正常性バイアス」とは、多少の異常事態が起こっても、それを正常の範囲内であるととらえ、心を平静に保とうとするはたらきのことだそうです。
例えば、朝起きて少しくらいのどがイガイガしていても、この「正常性バイアス」がはたらくために、「コロナになったんじゃないのか!どうしよう?」とパニックになることなく、「最近、乾燥してきたから風邪の初期症状かな。今日は体調管理に気をつけて過ごすようにしよう。」みたいな感じで冷静に対処することができます。
心のストレスを軽減させるバリア機能ですので、悪い事ばかりではないのですが、これがくせもので、せっかくいろんなサインが出ているのに、「私は大丈夫。」といってそのサインを見落としてしまうのです。
それが災害避難の際には、逃げ遅れにつながるということでした。
思えばそれは、災害避難の場だけではありません。
仏教では諸行無常を説きます。いつ終わるか分からないいのちと聞き、確かにそうだとうなずきながらも、色んな事を明日へ明日へと先延ばししている私であります。
せっかく「いつ死ぬか分からんとよ。今しかないとよ。」と教えてもらいながらも、「そうはいっても人はそんな簡単には死ぬもんじゃない。今までずっと大丈夫だったから、今回も大丈夫だろう。」と聞き流してしまうのです。
ただ、そんな私でもうっかり聞き流せないときがあります。それが身近な方、大切な方の葬儀の場です。そのときばかりは、素直に「そうでしたね。」と諸行無常の理を受けいれる私がいます。ふだんは法を聞き流してしまう私に、自然に法を聞かせる場が葬儀の場なのです。
私は住職ですから、葬儀の際は、御門徒の方を送らせていただくことが圧倒的に多く、亡くなった方をお敬いして大切に葬儀を勤めるのですが、ご遺族だけでなく送らせていただく私自身にとっても葬儀の場は本当に大切なのです。
今回は校区の防災に関する研修会ではありましたが、改めて、大切なことを気づかされたご縁でありました。
読む法話「まなざしの中で」 (西原村 益北組 慈雲寺 工藤恭修)
TBSアナウンサーの安住紳一郎さんがレギュラーで持たれている『日曜天国』というラジオ番組の中で、一つお題をあげてそのお題に視聴者の方々がそれぞれの思い出など投稿するというものがあります。たまたま聞いた時のお題は「捨てられないもの」57歳の男性の投稿でした。
「母が亡くなって7年、父が亡くなって1年半が過ぎ、ようやく私は実家の整理をしようと重い腰を上げました。やり出してみると性格なのか息子だからか、そこまで両親の持ち物に興味や愛着はなく写真など一部を除いて意外とスムーズに断捨離ができました。
そんな中、母の部屋の洋服タンスの上にポツンと置いてある一つの箱を見つけました。箱を開けてみると中には私の小学校1年生から高校3年生までの通信簿と中高で所属していた野球部のユニホームが入っていたのです。
通信簿なんて妻や子供たちに自慢できるような成績でもなく、そして今より15キロも痩せていた時のユニホームは現在着られるはずもなくすぐに捨てようと決めたのですが、箱の中に一通の便箋を見つけました。
その便箋には母の字で「こうさん、よく頑張りました。私の宝物です。」と書かれていたのです。勉強もできず、野球もレギュラーではなく、本当に出来の悪い息子だったのに。忘れた頃の母の自分への愛情というものはまたグッと来るものですね。そんなことを言われた日にはさすがの私も捨てるに捨てられず私の部屋の押し入れで現在幅を利かせることになりました。姿なき親の愛情を感じています。
この男性、自分の事を出来の悪い息子だとずっと引け目を感じていました。立派な息子に、立派な夫に、立派な父親にならなければならない。だけれども、そうはなれない自分がいた。その思いを抱える中にお母様の「よく頑張りました。私の宝物です。」の言葉にであい、救われたのではないでしょうか。
捨てたいと思っていた過去が「捨てられないもの」に変えられたのです。自分の全てを見てくれていた、受け入れてくれていた母親のまなざしに、母の願いに。
阿弥陀仏という仏さまは私に「立派な人間になれ。何かを成してこい」とはおっしゃいませんでした。「あなたらしく生きなさい。あなたがどんな生き方をしていようとも、どんな心持ちでいようとも私が一緒にいるから大丈夫。」とそのまなざしで常に私を照らし続けて下さる仏さまです。
辛い時も苦しい時もあるのがこの人生です。その中で時に「私なんて」と自分自身を虐げる事もあるでしょう。ですが、その私を決して見捨てる事などありません。
阿弥陀仏のまなざしの中に生きるとは、過去・現在・未来とこの私を見抜いた上で、このいのち尽きる時「よく頑張りましたね。」と褒めていただける人生を歩んでいるということ。その人生を「南無阿弥陀仏」というのです。
読む法話「ほんとうのこと」 (氷川町 種山組 西福寺 三原哲信)
以前、ある住職さんから「未来の住職塾」への参加を勧められました。この「未来の住職塾」は、さまざまな宗派のご住職や住職候補者が参加し、お寺の持つ潜在的な価値や、社会の変容を捉え僧侶の本来的な役割を探るカリキュラムです。私が参加した熊本クラスは、西本願寺熊本別院で開催されました。
主に九州全域からさまざまな宗派の若手僧侶や坊守さまが参加されました。お昼から夕方まで塾長の講義やワークで学びを深めますが、せっかく九州中から集まっていたので、閉講後は皆で毎回食事に出かけます。その懇親会の場では、ある暗黙の了解のようなものがありました。それは、自身の宗派の教えについては話をしすぎないように…というものでした。なぜならば、自分の宗派の教えについて熱く語るうちに、最終的にはせっかくの雰囲気を損なうことがあったからだそうです。しかし私たちの熊本クラスは、講義外でも独自に参加者のお寺を訪ねるくらい仲が良かったので、かなり踏み込んで、それぞれの宗派の教えについてお話を聞く機会がありました。
その場でのことです。何かのきっかけで祈祷(きとう)の話になりました。伝統仏教教団とはいえ、古い宗派から江戸時代に成立した新しい教団までありましたが、どの宗派にも一様に「願いごとが叶う」という教えと、それにまつわる祈祷法のようなものがありました。その話の脈絡の中で真宗の祈祷について聞かれましたが、私は真宗には祈祷がないのだと答えました。なぜ祈祷がないのかと問われたので、私の願いを叶えても私は本当の意味において幸せにはならない。なので真宗は、阿弥陀さまの御本願という願いの中に色あせない豊かさや幸せに出あわせて頂く教えだから祈祷がないのです、というようなことをお答えしました。しかし、どの宗派の方もピンとこられませんでした。むしろ「どうして仏教なのに、願いが叶わないのですか」「祈祷がない宗派があるって知りませんでした」と、不思議がっておられます。その時ふと思ったことは、よくも願いごとが叶わない浄土真宗のお寺がなくならなかったものだなということでした。遠い昔、願い事も叶わない教えやお寺なら必要ないと、淘汰されてもおかしくなかったかもしれません。しかし浄土真宗は日本で最も大きな宗派になりました。そして大きさだけではなく、真宗寺院は今も聞法の道場としてたくさんの人に色あせない豊かさをもたらし、私たちのお寺には生と死を超える営みがあります。
ならば先人は何を大切に思い、私たちのお寺を残してきたのでしょう。いろいろなことが考えられますが、親鸞さまによってあきらかにされたお念仏の教えは、自己中心的な願いごとが叶うどころではなく、私の生と死の意味が仏智によって変えられます。このことに出あった方々が、「これこそが大切だ」「このことひとつを、あの人に」と残してくださったのだと思います。私たちのお寺はきっと今日まで『ほんとうのこと』をつむいできたのです。この教えや受け継がれてきた私たちのお寺を、次の世代に伝え残してゆきたいと考えています。
読む法話「「また来るけんね」は母のよび声」 (八代市 種山組 大法寺 大松 龍昭)
九十を過ぎて次第に認知症が進んで以降、母は長姉の家に住まいを移し、そこで最後まで過ごしました。
亡くなる二か月ほど前のことです。発熱して母は近くの病院に入院しました。姉は母が寝たきりなることを心配し、熱が下がったら一旦退院させ、リハビリができる通所していた施設に移すつもりでした。しかし、私がその病院に初めて足を運んでその母の姿をみた時、「これはここを出ることはあるまい。きっとここが最後になるだろう」と私なりに気づきました。私はこれまで亡くなったご門徒さんの姿に何度も出あってきましたが、そのご門徒さんの姿とその時の母の姿が、完全に重なって見えたからです。なのでそれからは「次はない。これが最後なのだ」と自分に言い聞かせて見舞っていました。
ところが結果的に最後の見舞いとなったその日、看護師さんが「だいぶ食欲が落ちられました」と仰ったので、私は母に「ご飯は無理してでも食べなあかんよ」と声をかけ、母も理解したかのように二、三度頷きました。そしてその日、私は帰り際に母に「また来るけんね」と言ったのです。
確かに見舞いの帰りに「二度と来んけんね」と言って去る人はいないでしょう。「次に来るまで元気にしていてね」という思いで「また来るけんね」と言うのは、至って普通なことです。しかし、「次はない、これが最後だ」と自分に言い聞かせていた私は、この言葉がこの口から出たことに愕然としました。
この命は先送りなどできないものであること、明日とも今日とも知れない命をいま不思議にも生かされていること、したがってこの今を決して疎かにしてはならんのだということをこれまで何度も学んできたつもりだったのに、この口は「また来るけんね」と間違いなく言ったのです。
私は「やはりそうか」とつくづく思いました。どれほど大切なことですら、やすやすと忘れてしまう身の上の事実を忘れていたことを。だからこの命が尽きるまで、大切なことは繰り返し気づき直していかねばならないということを、また改めて母から学ばせてもらったのだと思ったことです。
そしてもう一つ思ったのは、「また来るけんね」は私が言うべき言葉ではなかったということです。親鸞聖人が「つつしんで浄土真宗を案ずるに、二種の回向あり。一つには往相、二つには還相なり」と明かされている通り、阿弥陀仏より施された(回向)お念仏の道とは、この私がお浄土へと行き生まれて仏と成る(往相)と同時に、仏と成るがゆえにこの娑婆世界に必ず還ってくる(還相)ということでありました。
どのようにしてこの私が仏縁に出あったかということについては、それぞれに背景がありましょう。ただ、自ら求めてというよりは、私が図らずして誰かに導かれて気がついたら出あっていた、ということが多いのではないでしょうか。例えば、あの人との別れという悲しみと痛みが縁となってこの教えに出あった、ということも少なくはないでしょう。
だとするならば、その私が称えるお念仏はそのまま仏と成った亡き方のお陰でこぼれたお念仏であり、その合わさった両手もまた仏と成った亡き方のお陰で合わさった両手ということになりましょう。そしてそこに気づかされてくると、この私の称えるお念仏の中に、この私の合わせた両手の中に、そのはたらきにいつだって出あえるのだということも明らかになってくるはずです。つまり仏と成った亡き方とは、私がお浄土に生まれねばあえないのではなく、いまここであえるということです。「還ってくる」とはそういうことを意味しているはずで、姿・形として見えてくるのではなく、はたらきとして感じ取り、聞き取っていくものだと私は思います。
そういう意味において、「また来るけんね」はそもそも私が言うべきものではなかったのです。「気づいている通り、私の死はもう間近だよ。でもね、心配はいらない。この命終えて速やかに仏と成って、貴方がお念仏を称えるその口元に、そして貴方が合わせるその両手の中に、必ず繰り返しまた還ってくるからね、そのことにどうか気づいておくれね」という、母のよび声でありました。そのように味わえた時に、母との別れがより一層尊いものに思えたことでありました。
読む法話「親しき友」 (嘉島町 緑陽組 法源寺 松本浩信)
他力とは他人の力ではなく、阿弥陀さまの本願の力です。本願とは阿弥陀さまの「根本の願い」すなわち「生きとし生けるものを救わずにはおれない」という強い願いです。その働きを他力というのです。そして、阿弥陀さまの本願を深く信じて疑わない心を信心というのです。
親鸞聖人は、
「他力の信心うるひとを うやまひおおきによろこべば すなわちわが親友ぞと 教主世尊はほめたまふ」
(『正像末和讃』)
と、ご和讃に記されました。お釈迦さまのお姿を経典より頂かれ、親鸞におきても同じ思いであることを伝えられたのです。
『仏説無量寿経』の下巻に『往覲偈(おうごんげ)』という偈文(げもん)があります。その後半に、お釈迦さまが敬い慶ばれ褒められた「親しき友」のことが書かれています。
「人のいのちはなかなか得がたいものだが、
それでも仏に遇うことはなお難しく、
信心の智慧を得ることはなおさらである。
ゆえにもし法を聞くことができたなら精進してさらに求めるがよい。
教えを聞き心にとどめてそれを忘れず、
仏を敬い信じて慶ぶものは、すなわちわが善き親友なり。」
得がたくして得たいのちは、明日をも知れぬ儚いご縁です。そのいのちは、多くのお陰さまに生かされています。そのひとつが食事です。私ひとつのいのちを支えるために、多くのいのちを毎日頂いているのです。
娘が中学生のとき、保護者会の手伝いをしていました。その時、教頭先生から
「ちゃんと給食費を払っていますから、うちの子には、給食の時、いただきますと言わせないでください」
と電話を掛けてきた保護者のことを伺いました。思わず笑ってしまったのですが、「いただきます」の大切な意味が伝わらない時代になったのかと、悲しい気持ちになりました。
そんな私たちに、ご縁を頂きみ教えに遇うことが出来たならば、
「精進してさらに求めるがよい。」
と勧めてくださいます。精進とは『聴聞の心得』に
一、この度のこのご縁は 初事と思うべし
一、この度のこのご縁は 我一人の為と思うべし
一、この度のこのご縁は 今生最後と思うべし
と示してあるように、いつ終わるとも知れないいのちのご縁を今日も頂き、み教えと出遇うことができたことを有難く勤めることです。
私たちは、見たり聞いたりしたことを、知識として覚えようとします。しかし、いつの間にか忘れてしまうことが殆どです。特に最近人の名前を思い出せないことがよくあります。「聴聞とは吸収すること」と言う言葉を聞いたことがあります。まさに阿弥陀さまのみ教えは、覚えることではなく我がいのちに向けられた阿弥陀さまの心願いそのままを受け取ることが大切なのです。
「教えを聞き心にとどめてそれを忘れず、仏を敬い信じて慶ぶもの」
親鸞聖人は、その姿を「他力の信心うるひと」と受け取られ、お釈迦さまが
「すなわちわが善き親友なり」
と慶ばれたことを、同じ思いであるとご和讃にて記されたのです。