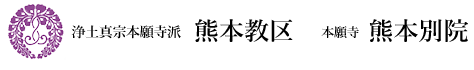法話集・寺院向け案内
2/13 全寺院向けご案内
・【教区】熊本教区僧侶寺族研修会(教区僧研) 開催案内
・【別院】本願寺熊本別院 春季彼岸会・総永代経法要
読む法話「遠仁者疎道、富久者有智」(宇城市 益西組 正壽寺 旭 啓寿)
漢字の読み替えで成り立つことばの面白さもありますが、仁(他から受けた事に感謝する心)に遠い人は道に疎い(道を間違う)、本当に心豊かな人は本当の智慧がある、つまり物事を正しく見つめる事ができる。という味わいのことばになっています。
節分といえば鬼がつきものですが、鬼とは元々「隠」と書いて、目には見えないけれど恐れたり不安の原因となるもの、つまり心の中にある良くない感情なども含めた意味のものでした。欲も怒りも手に負えない私も鬼である、という見つめ方もそこにはあったのでしょう。
私たちは日暮しの中で、どうしても私が中心の視点からものごとを見つめます。「かけた情は水に流せ、うけた情は石に刻め」(人の為に何かをしても忘れ、人からうけた恩は大事に)という訓語もありますが、むしろ逆に自分がした事ばかり手柄かのように覚えて、うけた様々なご恩の方を忘れる生き方をする私は「鬼」をかかえた姿といえます。
「智慧」とは、私を見つめ照らし出す仏様のまなざしによって、私の有り様を明らかにするはたらきです。明らかにしたうえで「あなたをかならず引き受ける」仏となって下さったのが、阿弥陀さまでありました。
「鬼」の私には仏様の智慧の眼の様な物事の見方はできませんが、お念仏にであい、仏様を拠り所とする歩みのなかで、自己中心の視点からほんの少し、まわりの多くの(お蔭様)で支えられた人生を歩んでいる私です。と受けとめながら、日々を味わえる私でありたい2月です。
1/23 全寺院向けご案内
・【教区】連研履修者研修会 開催案内
・【寺婦】寺族婦人基礎講座 開催案内
・【寺婦】第2回寺族若婦人研修会 開催案内
以下は1/9送付の再送になります。
ぜひお申し込みください。
・【仏壮】会員研修会 開催案内
・【教区】SNS研修会 開催案内
・【仏婦】第2回次世代育成にかかる研修会 開催案内
2026/1/9 全寺院向けご案内
・【教 区】SNS研修会開催について(ご案内)
・【仏 壮】仏壮会員研修会開催について(ご案内)
・【仏 婦】第2回次世代育成にかかる研修会開催について(ご案内)
・【ビハーラ】くまもといのちの電話 自殺予防公開講演会について(ご案内)
なお、このたびは郵送にて次の書類をお送りいたしております。
・布教団第二支部布教大会チラシ(2026/1/30)
新年のご挨拶 熊本教区教務所長・熊本別院輪番 大辻󠄀子 順紀
慈光迎春
お念仏とともに新年を迎えられましたこと、お慶び申しあげます。
さて、昨年は先の大戦終結から80年の節目の年でございました。終戦から80年以上経った今日、実際に戦争を体験されている世代が高齢化し、数少なくなられていることに加えて、これまでに経験したことのない異常気象が甚大な被害をもたらす自然災害に毎年のように直面するなどによって、戦争がもたらした計り知れないその悲しみは過去のこととして忘れ去られ、近い将来、平和実現のための取り組みが後回しになってしまうのではないかとの強い懸念を抱くことでございます。
80年前の7月1日そして終戦間近の8月10日、ここ熊本も大空襲を受け469人もの尊い命が犠牲になりました。終戦末期はこのように日本各地で空襲が激化し、全国で41万人もの民間人が犠牲になったと言われています。
そしてその終戦から80年の現代にあってもロシア連邦によるウクライナへ軍事侵攻やイスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突、イスラエル・イラン相互の軍事行動、そこへアメリカの軍事介入など、各地の紛争、内戦、争いは絶えることなく、罪のない多くの人々が命の危機に晒されています。
この日本においても「台湾有事」への備えと称して沖縄県の離島や鹿児島県の島に自衛隊基地が建設されており、さらには昨年の国会における首相の「存立危機事態発言」によって日中関係が冷え込み、決して「対岸の火事」ではありません。
言うまでもありませんが、戦争は人間によるもっとも愚かで醜い所業であり、いかなる理由があろうともそれは決して正当化されるものではなく、絶対に許されるべきことではありません。武力によって真の平和を実現することは、できないのです。しかし、私たちは長く続くことでそのことに慣れてしまい、関心が希薄になっていくことこそが、私たちにとって最も恐れなければならないことであり、無関心が私たちの最大の敵であり脅威であります。
釈尊は『法句経』に「己が身にひきくらべて、殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ。」と、どこまでも非暴力を貫く生き方をお説きくださいました。しかし我が教団は、先の大戦に積極的に加担したという過去の事実があります。そうした過去を謙虚に反省し、戦争がもたらす痛ましく悲惨な事実や数えきれないほどの悲しい死別の上に私たちが生かされているということ、犠牲になられた方々の無念さや思いを背負っていく責務があるということを次の世代へしっかりと伝えねばなりません。
そして親鸞聖人のお示しくださいました「世の中安穏なれ仏法ひろまれ」また「御同朋・御同行」とのお心にかなうよう、お念仏申させていただきながら、自他ともに心豊かに生きていくことのできる「非戦平和」の世界の実現に微力ながら努めさせていただくことでございます。
本年もお念仏を慶ばせていただきながら職員とともに精進してまいりますので、皆さまには引き続き、ご教導たまわりますようお願い申しあげ新年のご挨拶といたします。
合掌
12/11 全寺院向けご案内
・【教区】メール配信システムへの登録について(ご案内)
・【布教団】一日研修会【公開講座】開催について(ご案内)
なお、このたびは郵送にて次の書類をお送りいたしております。
・教区報第201号
・少年連盟だより第3号
・布教団第一支部布教大会チラシ